八王子まつりといえば、今や関東を代表する夏まつりのひとつ。
けれど「いつから始まったの?」「なぜ山車が主役なの?」と歴史に興味が湧く人も多いはず。
今回は八王子まつりの成り立ちや山車のルーツ、そして元横山町の山車について、分かりやすく解説します。
八王子まつりはいつから始まったの?
今の「八王子まつり」が生まれたのは、”1961年(昭和36年)”に「3万人の夕涼み」として市民祭が開かれたのがきっかけです。
当時の八王子は人口急増の時代で、旧住民と新住民の交流や地域愛を深めようとスタートしました。
最初は花火大会や演奏会が中心の、のどかな夏の夕涼みイベントでした。

現代の八王子まつりは昭和36年に始まった新しいお祭りなんだって!
八王子まつりの名前と規模が広がったワケ
1964年からは、祭りの会場を甲州街道へ移しパレードも導入。
1968年には「八王子まつり」として本格始動し、地元町会の山車も正式に参加するようになりました。
「市民祭」から「八王子まつり」へ——そして今の3日間の大規模イベントへと成長しています。

最初は小さな市民祭り、だんだん今の大規模な“山車まつり”になったんだね
八王子の山車祭りのルーツは江戸時代
八王子まつりの象徴といえば山車(だし)。
当時の八王子は甲州街道の宿場町として栄え、「下の祭り(八幡八雲神社)」と「上の祭り(多賀神社)」という2つの神社の祭礼がありました。
それぞれ7月と8月に分けて開催され、各町の山車が華やかに練り歩いたそうです。

山車祭りの伝統は江戸時代後期から続いてるってすごい!
上の祭りと下の祭り ― 二つの神社と山車
八王子山車まつりのもとになったのが、多賀神社の「上の祭り」(現・元本郷町エリア)と八幡八雲神社の「下の祭り」(元横山町エリア)。
この二つの大きな神社のお祭りでは山車や神輿が各町から出て、お囃子や賑やかな掛け声とともに町中を練り歩きました。
そして1968年の統合を経て、八王子まつりの山車巡行に発展しています。

上=多賀神社、下=八幡八雲神社。2つの祭りが合体したんだね!
山車の進化と八王子ならではの“人形山車”
中央に「心柱」を立てて、精巧な人形を載せる豪華な造りが特徴。
町の豊かさや職人の技も競い合い、町ごとの個性が光っていました。
山車には、地元の宮大工棟梁が携わっていたそう。
今もその伝統が山車の装飾やお囃子、ぶっつけ(山車同士のお囃子対決)に受け継がれています。

江戸時代の人形山車、技とアイデアの詰まった豪華絢爛な歴史遺産!
元横山町の山車とその魅力
「元横山町」の山車は、下の祭りの拠点となった八幡八雲神社にゆかりのある町のもの。
八王子市内でも歴史が古く、細やかな彫刻や立派な人形飾りが見どころです。
祭り本番では独自のお囃子や威勢のよい曳き回しも話題になっています。
地域の子どもたちや住民が一体となって曳くこの山車は、八王子の伝統の“生き字引”といえる存在です。

元横山町の山車、伝統と地元愛がいっぱい!八王子まつりの花形だよ
まとめ:八王子まつりの歴史を家族や友達と楽しもう
- 現在の八王子まつりは1961年に誕生
- ルーツは江戸時代の町ごとの山車祭り
- 上の祭り(多賀神社)・下の祭り(八幡八雲神社)を統合
- 山車は各町の個性と歴史、職人技の結晶
- 元横山町山車は下の祭りの伝統の象徴
歴史を知るとお祭りの見どころがもっと増えます。
ぜひ祭り当日は各町の山車と元横山町の勇壮な姿もお見逃しなく!

歴史を知ればお祭りがもっと楽しい!山車と一緒に八王子の夏を満喫しよう
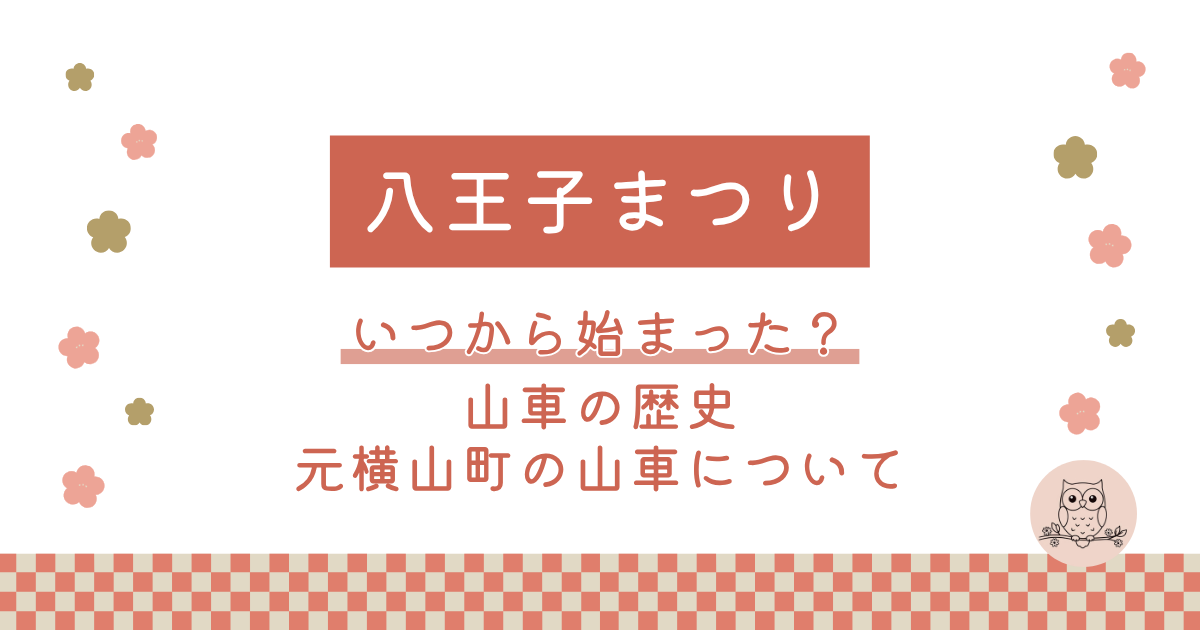

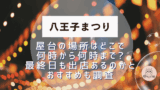

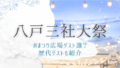
コメント